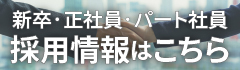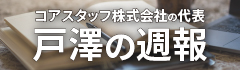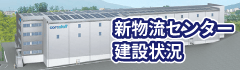戸澤の週報
2025年04月05日
不確実性の時代に必要な戦略とは
不確実性の時代に必要な戦略とは
今まで多くの戦略論の本を読みました。
それこそ100冊はゆうに超えると思います。
一般的な戦略論の書籍は、きちんと前もって戦略と呼べる形を作ることを勧めています。
市場を分析し、自社の強みと弱みを分析した上で、他社と差別化をして製品を市場に投入する。
そして、リーダーに依存しない再現性の高い仕組みにすることが重要である。と言った内容です。
しかし、本当にそれで良いのでしょうか?
心のどこかで違和感を持っていました。
精緻な戦略を始めから作ったところで、実際にはほとんどその通りにことが進まないのが現実です。
今回出会った三品和宏さんの「経営戦略を問いなおす:ちくま書店」は今までの概念を変えてくれる内容です。
著書の中で、戦略の本質は「為す」ではなく、「読む」にある。経営者が持つ時代認識こそ、戦略の根源を成すとあります。
この発想は、従来の戦略論とは一線を画しています。
多くの方のイメージは、戦略とは何かしっかりとした方向性なり、内容を決めてから活動を開始するではないでしょうか?
しかし、その場合ですと、果たして何を元に戦略を作ればよいのでしょうか?
経営をしていると、痛いほど実感するのは、「不確実性との戦い」が経営の本質であると言うことです。
もちろん事前に能動的に様々なことを想定し、用意しておくことは大切なことだと思います。
しかし、それを戦略にしてしまったら、想定外のことが起こった瞬間に無力なものになってしまうと思うのです。
三品さんは「戦略は経営者の頭の中に宿る」と述べています。
毎日起こる様々な予想外の新しい展開にリアルタイムで何とか対応していき、それが結果として戦略になる。
従来の戦略論が能動的戦略観と言うのであれば、この考えは受動的戦略観と言えるでしょう。
一見して何ら関係のないような様々な幾多の案件に判断を下し、全体を進めていきます。
外の世界からの会社を狙った弾は常に様々な角度から飛んできます。
それらを経営者は次々にかわしていき、判断を行うその中にこそ、実践的な戦略が生まれてくると言うことです。
こちらの考え方は経営者だけではなく、どんな組織のリーダーにも当てはまりそうです。
どんな名文でも、実際の現場で役に立たなければ意味がありません。
リーダーに必要なことは作文力ではなく、時代時代の現場から風の向きを読み切ることです。
苦労して出来上がった形こそ、自社の戦略になると言うことです。
素晴らしい読後感の本でした。