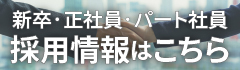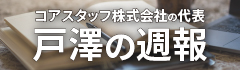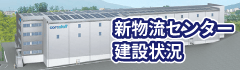戸澤の週報
2025年02月01日
バタフライ効果
先週は年1回の1人合宿に行って来ました。
過去の振り返りを行い、現状の再認識をします。
過去の意思決定が効果を奏していることもありますが、逆になっていることもあります。
うまくいっていない場合は早期に認めた上で、改めることが大切です。
一度決めたことを戻したり、別のものに変えることは様々な理由で難しいものです。
変えるためには労力がかかります。
間違っていたことを認めることに対する抵抗もあります。
完全に間違っているのであれば、動きやすいのですが、たいていは良い部分と悪い部分があり、悪い部分が目立っているなと言った状況です。
良い部分も失ってしまうのではと言う恐れもあります。
しかし、たいていのアクションプランは一度で完全に成功することなどありません。
PDCAを繰り返すことが大前提である考えると、失敗と言う認識ではなく、成功までのプロセスと言った捉え方ができます。
成功するまで様々な検証を繰り返し、あきらめずにリトライを繰り返していきたいと思います。
合宿の中で学んだことのひとつに「システム思考」と言う考え方があります。
事業を取り巻く環境を一つのシステムとして捉えます。
会社において一つの目標を達成するためには、多くの人が関わり、様々なアクションを取り、全員が成果に向かって進みます。
しかし、結果としてうまくいかず、最悪の場合は現状より悪くなったと言うことが起こります。
これは、我々を取り巻いている環境が、こうしたらこうなると言った単純なものではなく、非常に複雑に様々な要因が互いに影響し合っているからです。
例えば、営業のインセンティブ制度を考えてみましょう。
売上に合わせて何らかの報酬が変わってくるのであれば、目先の売上を上げることに集中することになります。
その結果、従来行っていた、顧客のすぐには売上に繋がらないような要求に応えなくなり、長期的な顧客との関係性を構築できなくなります。
結果的に顧客満足度が下がり、売上が下がってしまいます。
このようにこうやったらこうなると思ってやったことが、意図と異なる結果を生む現象のことをシステム思考では「創発現象」と呼びます。
我々を取り巻いている環境が複雑であればあるほど、創発現象が良く起こります。
昔からある電池式の懐中電灯であれば、システムが非常に単純で、もし壊れたとしても、私でも原因を特定できて直すことができるでしょう。
しかし、現在の最新の航空機の不調を、一般の人が簡単に原因を特定し直すことができるでしょうか?
現代の環境を考えてみると、30年前に比べてより複雑になっていることが分かります。
インターネットが浸透し、情報のコモディティ化が進んでいます。
生成AIの誕生で、より加速しています。
SNSの存在が、良くも悪くも企業への影響度をより大きなものにしています。
役割の分業化が進み、プレイヤー間の思惑も複雑に絡み合っています。
人材の確保や、インフレ、政治の不安定や、戦争問題など、少し考えただけでもシステムをより複雑にするマクロの要因がたくさん出てきます。
それならば、そもそも、一回で最良の結果を出そうと考えること自体がおこがましいものではないか、と考えるに至りました。
この複雑なシステムも理解するには、全体像を俯瞰して捉えることももちろん大切ですが、個人的には現場でよりミクロで捉えていくことが大事だと思います。
現場が日々接している顧客からのフィードバックは、より複雑になったシステムからの答えなのです。
全社として、営業現場として取ったアクションに対して、顧客は常にフィードバックを返してくれているのです。
現場で答え合わせをきちんとするためのツールを持たせ、その結果自分たちのアクションを決定できる自律的な組織になることが必要です。
毎日、毎週、毎月、毎年の単位できちんと顧客からのフィードバックを答え合わせする仕組みこそ、複雑なシステムに対する一つの解であると考えるに至りました。
題名のバタフライ効果とは、ブラジルの気象学者であるエドワード・ローレンツ氏が1972年で行った講演で「ブラジルの1羽の蝶の羽ばたきが、テキサスで竜巻を起こすか?」と言う問いかけに由来します。
気象と言う超複雑なシステムに対しては、小さな蝶の羽ばたきの力がより大きな気象現象に繋がる可能性を完全に否定できないと言うことです。
こんな発想が50年も前からあったのですね。
何を今まで勉強していたのかとちょっと複雑な気持ちになってしまいますね。